
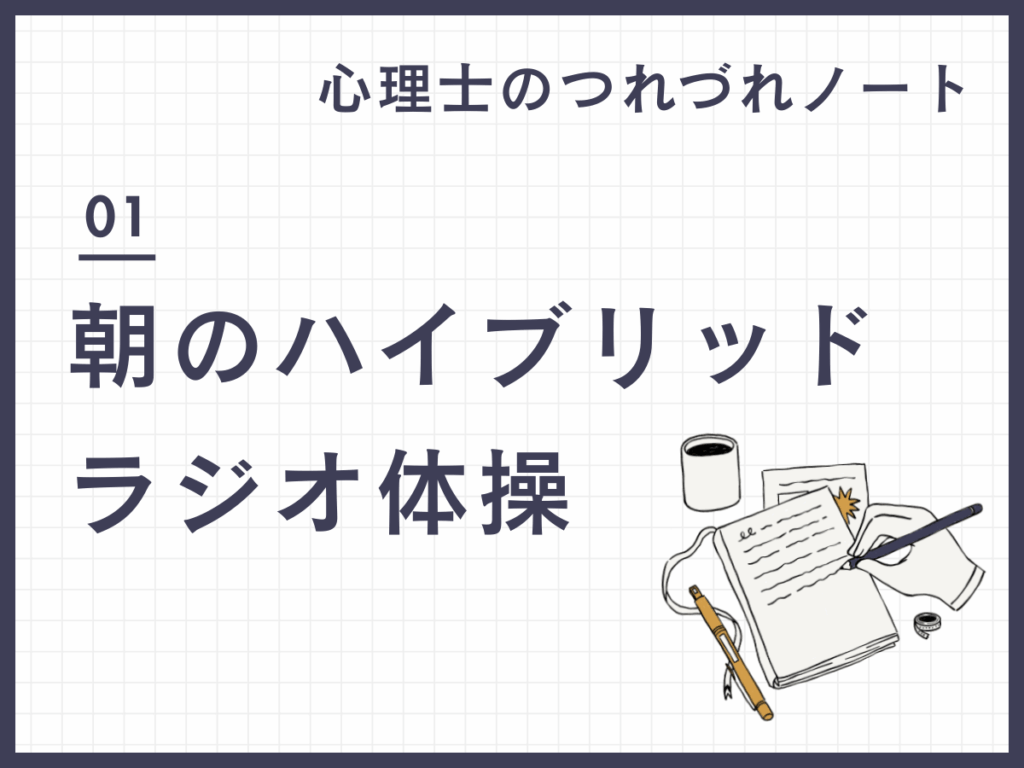
わたしはジョブトレで心理士をしています。
これから、利用者さんたちがここでどんなことをしているのか、どうやって自立に近づいていくのか、心理士の目線でお伝えしていこうと思います。
ジョブトレは午前10時から始まります。 そこには「はじまりの合図」があります。
コロナ禍で緊急事態宣言が出され、利用者さんがジョブトレに通えなくなったとき、「オンラインでラジオ体操をしよう」という提案がありました。
利用者さんそれぞれが自宅で、スマホやパソコンからZoomのミーティングに入り、ビデオや音声のオンオフも自由に決めて「いっしょに体操をする」作業開始のプログラムです。
ふつうのビデオ会議と同様、パソコンの画面はつながった参加者とスタッフの小さな四角形で埋め尽くされていました。
真っ黒な四角に白抜きの会議ネームが居並ぶ中、定番「ラジオ体操第一」のメロディが流れる、なかなかシュールな絵柄ではありました。
この習慣は利用者さんがジョブトレのフロアに戻って来てからも続いており、午前10時にみんなでラジオ体操をして一日をスタートする流れとなっています。

ジョブトレのフロアがある1階と、スタッフのいる2階に、朝イチでラジオ体操の音声が流れます。
パソコンも1台つないであり、オンラインの先にはほかのプログラムの参加者やすでに働くようになった若者などが、自宅から参加してきます。
一般的には「始業時間に社員が集まって仕事が始まる」という何ということもない流れですが、これにすんなりと乗れない方は珍しくありません。
時間を守ることが苦手な人にとっては、朝、決められた時間までに来所することは難しく感じられるでしょう。
集団が苦手な人は、利用者・スタッフがひしめく場所に入れなかったりします。
あるいは、音楽に合わせて、他の人と同じ動作をすることに抵抗感を感じる人、必然性を納得できないと行動に移せない傾向の人もいます。
「誰でもできる普通のこと」と思われている決まりは、実はちっとも当たり前ではないかもしれません。
つまり、もうここから就労のための訓練が始まっているわけです。
スタッフは体操やフロアに入ることを強要はせず、見守ります。
しばらくは会場の隅で背を向けていたり、入り口で体操を観察したりしながら、ほとんどの人は少しずつその場に近づいていきます。
それまでに要する時間も過程も、人さまざまです。
「体操はしたくないけど作業はする」という利用者さんの場合、体操を省略して清掃などに従事してもらいました。
すると、次第にしぶしぶ体操もするようになり、無事仕事をみつけていったのです。
ジョブトレを経て就労を実現した若者たちが自立を果たしたエピソードは、おいおい詳しくお伝えしましょう。
ラジオ体操の5分間だけでも、そこは社会への入り口です。
朝早い電車に揺られ、駅からの近くない道のりを、雨の日も盛夏でも歩いて来所し、作業服に着替えてみんなといっしょに腕を伸ばしたり腰を回したり。
同じ動作をしながら、私たちスタッフはみなさんの小さくない奮闘に、日々、敬意を抱いています。
(育て上げネット・ユースコーディネーター、公認心理師 田中有)
